

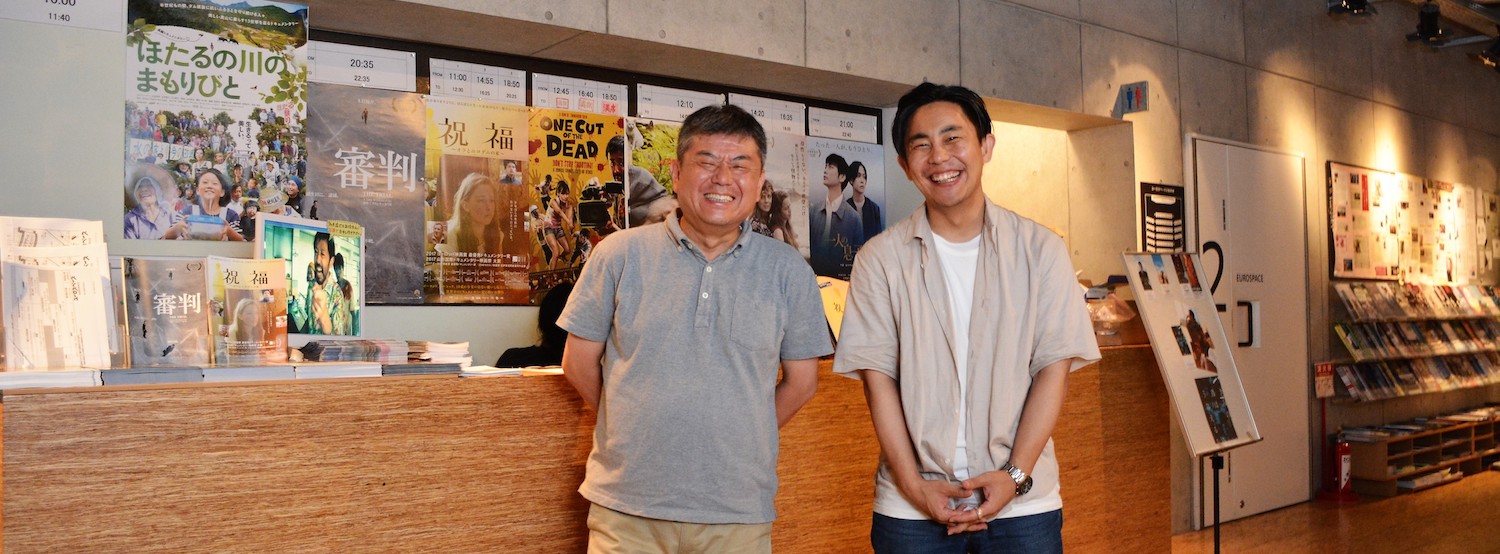

渋谷駅ハチ公口から徒歩10分弱。飲食店やライブハウスなどが立ち並ぶディープな一角に、「ユーロスペース」という映画館があるのをご存じだろうか。1982年に同区桜丘に開館して以降、36年にわたって渋谷のミニシアターカルチャーをけん引してきた存在だ。娯楽の多様化やデジタルデバイスの普及などで、映画鑑賞の形が変わる今、アート映画を世に送り出してきたミニシアターも次の時代を見据えた変革を迫られている。
そもそもミニシアターはどういう経緯で始まったのだろうか。開館当初と現在の映画を取り巻く環境の違いをどう捉えているのだろうか。クラウドファンディング「Motion Gallery」や、カフェなどで気軽に自主上映会が開催できるプラットフォーム「popcorn」など、映画文化を支える仕組みを次々に生み出している大高健志さんが、ユーロスペースの支配人・北條誠人さんに聞いた。
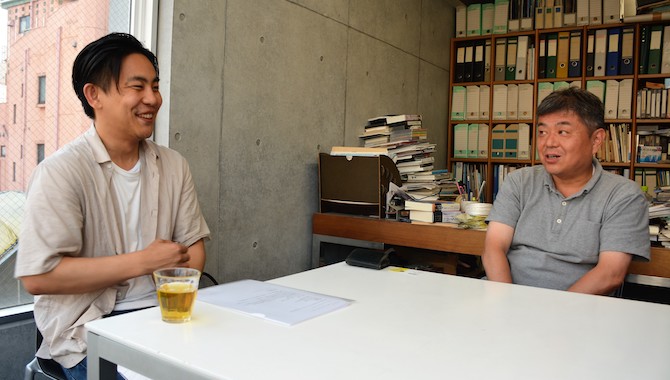
左:大高健志さん 右:北條誠人さん
大高
本日はよろしくお願いします。まず初めに北條さんのご経歴から伺っていきたいのですが。
北條
出身は静岡です。高校のころから同級生の影響で映画が好きになったのですが、大学進学とともに上京してからは、岩波ホールをはじめとするミニシアターや名画座に足しげく通いました。自主上映活動をやっているご縁で「欧日協会(ユーロスペースの前身)でスタッフを探しているんだけど、大学卒業後どう?」と「アテネ・フランセ文化センター」の方から紹介があって、欧日協会の正規のスタッフになりました。
大高
じゃあ、ユーロスペースができるのと同じくらいに入社されたと?
北條
ユーロスペースが映画の常設館なったのはそのちょっとあとですね。いわゆるシネクラブという形で、自分たちの好きな映画を上映する集団が当時はありまして、アテネ・フランセ文化センターもそうだしユーロスペースもそういう形だったんですね。「岩波ホール」がその先駆けで、「名古屋シネマテーク」や岡山の「シネマ・クレール」なども、シネクラブから生まれました。
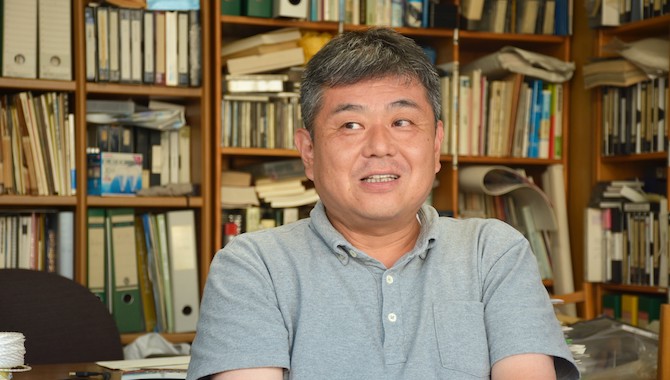
北條
ミニシアターの系譜の紹介になりますが、もう一つの流れが、「シネマスクエアとうきゅう」。新宿にできたミニシアターなんですが、そこは東急グループの興行会社の東急レクリエーションが、チェーンの映画とは違う映画を上映したいと言って始めたミニシアターです。
さらに、全く異業種が参入して出来た「シネ・ヴィヴァン・六本木」という映画館がありました。いわゆるセゾン文化の流れの中で出てきたミニシアターです。
シネクラブ型のミニシアターと、興行会社がアートフィルムをやっていきたいと始めた型と、異業種が「アートがビジネスになる」と考えて始めた型、ミニシアターにはこの3つの流れがあるわけですね。
大高
なるほど。それでは、ちょうど新しいミニシアタームーブメントが生まれてきたときにユーロスペースも誕生したと。その時もある種のカウンターカルチャーですよね。その時のメジャーっていうと?
北條
「日劇」です。大きなワンスクリーンでドーンみたいな。
大高
いまのシネコンのようなスクリーン数はないですが、そのときも大きな箱で大きな映画をかけていたと。
北條
「日劇」や「パンテオン」ではハリウッドの大作や日本映画の大作をかけていたんですね。そのような大作だけではなくて、例えばヨーロッパとかアジアとか、あるいは日本でもインディペンデントの映画があって、それをビジネスとして上映できる空間が、当時のミニシアターの考え方だったんです。
大高
じゃあ、今の「シネコンばかりでうんちゃら・・・」という話とある意味似たような話だったわけですね。
北條
そうですね。ですから今の地方のミニシアターは当時の考え方と非常に近いですね。シネコンで上映される作品ではない作品を、きちんと上映するという考え方のミニシアターです。

大高
そういう中にユーロスペースはあったと。ユーロスペースのコンセプトは、前身が欧日協会というくらいですから、ヨーロッパのアートフィルムが中心だったのでしょうか?
北條
最初はドイツなどヨーロッパの映画を買い付けてきて自分たちで上映するというスタイルでした。劇場ができる前はホールを借りて上映をしていました。
大高
ヨーロッパの上質な作品を届けることがコンセプトだったと。
北條
他のミニシアターではやらない、ヨーロッパの作品をピックアップしていこうという考え方でした。

大高
僕が知っているのは2006年に円山町に移転してからのユーロスペースですが、若手の邦画も上映していらっしゃいますよね。それは開館初期からそうだったのですか?それとも、途中から始めたのでしょうか?
北條
移転する前の桜丘のときから少しやり始めていましたが、いまは本数が多いですね。背景にはデジタルで映画を作りやすくなっているのと、学校が増えて作る仲間が増えているというのもあると思います。一方で、作ったものをみせるところはそんなに増えていないと。
大高
なるほど。
北條
これから出てこようとする人たちにとっては、劇場で上映されるか映画祭で認知されるかしかないですよね。

大高
たくさん上映希望が来ると思うんですが選定基準は?
北條
数が多くてとても観きれないです。なので、最近は「撮りました。上映を検討してください」って持ち込みがあると、「パソコンでもポータルのDVDプレーヤーでもいいから一緒に見ましょう」と言っています。私が隣でブーブー言いながら見ますけど。前のカットと次のカットが繋がってませんねとか、このセリフの主語はなんですかとか、言いながら事務所で作った人と一緒に見ています。
大高
その場でダメ出しするんですか?(笑)。そのなかで上映するかしないかの基準は?
北條
まずは、「きちんと人に伝わる物語ができているかどうか」が最低限の基準です。
あとはやっぱり画が強いかどうかが僕らの基準としてはあります。観たことのある画だと弱くなりますよね。それよりも独自のセンスで切り取る力が欲しい。それと役者のキャラクター付けは気になります。
大高
なるほど。それでは極端な話、ストーリーには・・・
北條
僕はそんなに重きを置かない。海外の映画祭に行くと、僕は語学能力が非常に低いのでどこを観るかといったら結局は「画」と「センス」。「構図」、「力」。
映画の文法は世界共通ですから、語学ができなくてもあまり関係ないと勝手に思い込んでいるんです。文法は同じなんです。語法は違っても。もう一方でいうと新しい語法が欲しいんです。
大高
会話がわかるかどうかではなく、画から伝わる圧力が重要だと。
北條
なにを彼らが伝えたいかっていうことです。このキャメラマンは何を撮ろうとしているのか、この監督はどういう雰囲気を醸し出して私たちにテーマなり物語を伝えようとしているのか。役者はどういうセンスで演技をしているのかっていうのがわかれば、僕は全然いいと思っています。その中で、強いものと新しいものを自分は求めている。

大高
話は変わるのですが、ユーロスペースとして思い出深い作品というと?
北條
いくつかあるのですが、一つ上げるとすれば、塚本晋也監督の『野火』。塚本監督が配給も全部自分でやっていて、横で見ていて勉強になりました。執念が違うんですよ。
大高
熱量を超えた執念だと。
北條
まさに執念。「この映画を観せたい、小さな劇場でもいいからとにかく自分は観せていくんだ」っていう執念がすごかった。
ベネチア国際映画祭に出品された後に塚本さんから私の携帯に電話がかかってきて、「『野火』っていう映画を作ったので上映についてご相談させてもらいたいんですけど」っていう。驚きましたね。もう次の日にお会いしてお話しして作品を拝見しました。塚本さんの希望は次の年、終戦から70周年の8月に上映したいと。やりましょうという形で決まりました。
執念は人に伝わっていい形で劇場公開に繋がるし、公開後もいい形で広がるんですね。
大高
確かにあの時は観なきゃいけない感がありましたよね。
北條
映画を作るということは人にメッセージを伝えることだと教わりました。

(取材・構成:大竹 悠介)

北條 誠人(ほうじょう・まさと
有限会社ユーロスペース 支配人
1961年、清水市(現・静岡市)に生まれる。法政大学経済学部経済学科卒業。大学在学中から映画の自主上映に携わる。85年にユーロスペースの前身「欧日協会」に入社。87年からユーロスペースの支配人となる。2006年に渋谷区桜丘にあった劇場を渋谷区円山町に移転。
劇場の支配人のほかにアキ・カウリスマキ監督の『希望のかなた』(2017年)などの自社の配給を担当したり、特集上映<原爆と銀幕―止まった時計と動き始めた映画表現>(2016年)を企画した。

ユーロスペース
アクセス:渋谷区円山町1-5 KINOHAUS 3F(渋谷駅下車、Bunkamura前交差点左折)
TEL:03-3461-0211
公式WEBサイト:http://www.eurospace.co.jp

大高 健志 (おおたか・たけし)
Motion Gallery代表 / popcorn共同代表
早稲田大学政治経済学部卒業後、外資系コンサルティングファームに入社。戦略コンサルタントとして、主に通信・メディア業界において、事業戦略立案、新規事業立ち上げ支援等のプロジェクトに携わる。その後、東京藝術大学大学院に進学し映画製作を学ぶ中で、クリエーティブと資金とのより良い関係性の構築の必要性を感じ、2011年にクラウドファンディングプラットフォーム『MotionGallery』を立ち上げ、2015年にグッドデザイン・ベスト100受賞。2017年にマイクロシアタープラットフォーム「popcorn」を立ち上げた。