



昨年2017年は映画業界にとってエポックメイキングな年となった。5月に開催された世界三大映画祭「カンヌ国際映画祭」では、大手動画ストリーミングサービス「Netflix」が製作した作品『オクジャ』(ボン・ジュノ監督)が公式コンペにノミネートされ物議を醸した。フランスには、映画はまず映画館で公開し、ストリーミングサービスはそのあとに行わなければならないという法律があり、フランス映画界がNetflixに反発した形だ。
さらに、12月には米ディズニーが大手スタジオの21世紀フォックスを買収し、多くのメジャー作品の権利を取得した。ディズニーは19年にも独自のストリーミングサービスを開始し、Netflixに対抗する構えだ。
映画の製作・配信の形態はストリーミングを中心に大きな変化を遂げつつある。この時代に、映画を観ると言う行為、映画を作ると言う行為はどのような変容を遂げていくのだろうか。テレビディレクターとして『ハゲタカ』(2009年)『龍馬伝』(2010年)などの演出に携わり、独立後に『るろうに剣心』(2012年)『3月のライオン』(2017年)などのヒット作を世に送り出して来た映画監督・大友啓史さんに訊いた。

大友啓史監督
Netflix, Amazon, Huluなど、日本でもオンデマンドでの視聴が普及しましたが、制作者と鑑賞者との関係の変化をどのようにお考えですか?
大友日本の鑑賞者は主体的にコンテンツを選択するような段階にはまだ行っていないのではないかと思います。オンデマンド配信は時間に関わらず、いつでも観られますが、いつでも観られると観なかったりもする。日本人は受け身でダラダラとテレビを観ることに慣れてしまっていて、海外では人気のサービスも日本では苦戦していますよね。ですが、僕らは次の時代に備えていなければならなくて、作り手側が観る側をどう引っ張っていくのかが重要なのだと思います。
欧米とは違う、日本ならではの発展形態というとどのような形が想像できるでしょうか?
大友前提として、映画は世に問う想いがあって行われる表現行為です。当然、作品を作って終わりではなく観てくれる人がいるのが前提です。観てくれる人が多数だと「商業映画」になり、そうでない作品は「アート映画」というわけ方ができます。いろんなジャンルがありますが囲い込みが進んでいるのが日本映画の特徴ですね。
たとえば?
大友AKBのコンテンツはAKBのファンが観る。競争が激しい商業映画の世界では、毎回応援をしてくれるコアな人たちの母数をどれだけ増やせるのかが重要です。作り手側は、お客さんとコミュニケーションをとりながら、アウトプットするメディアも含め、どういう形であれば目を向けてもらえるのか日々考えています。クラウドファンディングなどを通じて、今まで観るだけだった人たちにより主体的な形で参加してもらうのも、コアなファンを囲い込む仕掛けのひとつだと思います。
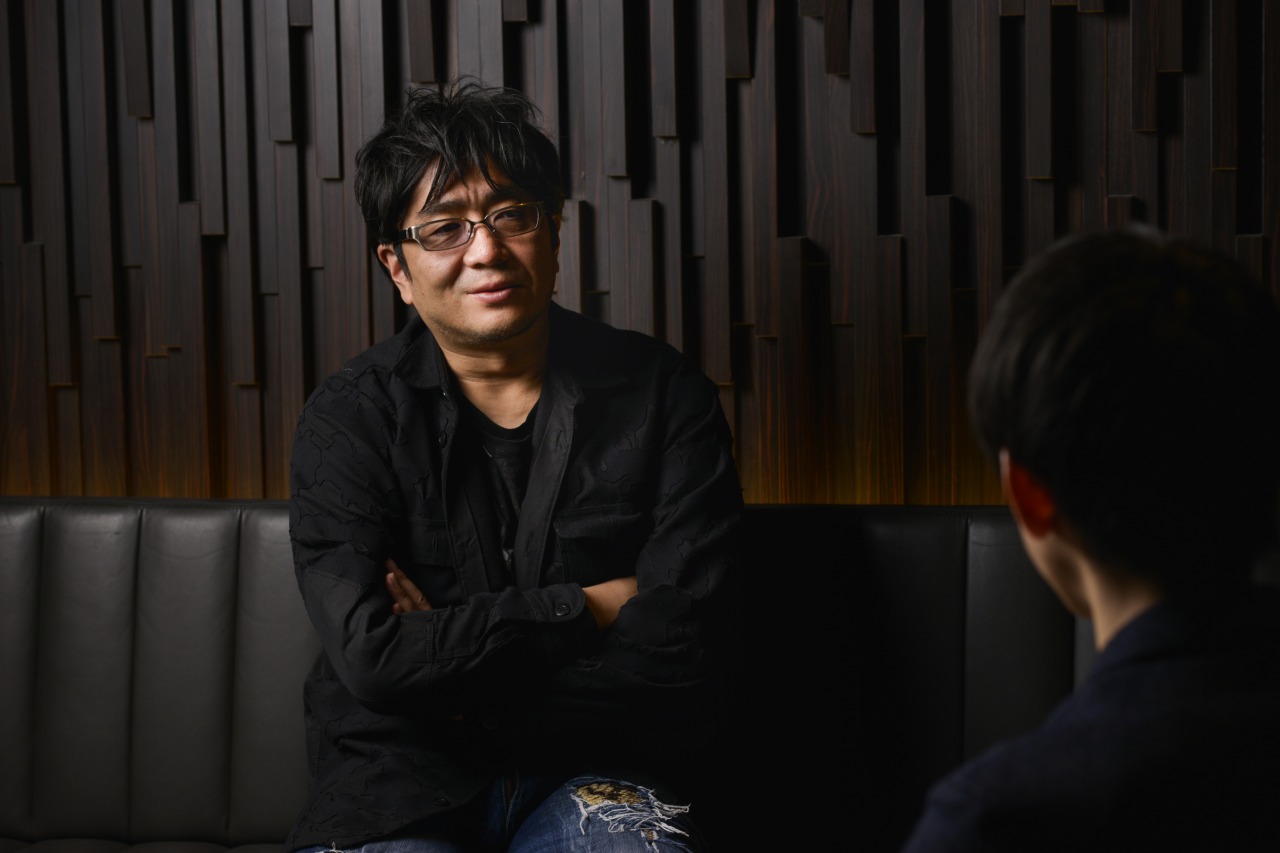
日本では、クラウドファンディングで製作資金の調達をした『この世界の片隅に』(片渕須直監督・2016年)のように、映画を観る人が消費者としてではなくパートナーとしての立場で映画に関わる流れがあると思います。
大友言葉を選ばずに言えば、個人の意志は簡単です。その人一人が納得すればいいわけですから。作り手としても想いを届けやすい。作品をつくる船出に際して、0から作るのはとても不安なわけですよ。そこで趣旨に賛同してくれて、名前と顔が見える形で応援してくれるのは力になりますよね。
対して企業がスポンサーとなると、何人ものハンコがないと出資は受けられない。企業の中の人たちが納得するには実績が必要ですから、全くの新人は支援を受けにくい。そう考えると、映画製作のファーストステップで個人が出資者となるのには大きな可能性を感じます。
個人が出資者になることで、作り手のあり方も変わりますか?
大友「お客さん」のスタンスを乗り越えて「参加」して来た方々に、次も参加したいと思っていただけるか。それを作り手が作り続けていく視点が重要だと思います。お金を出すからには、本当にその才能に価値があるのか、個人のパトロンは厳しく見ていますから。

大友映画は日本ではビジネスです。作り手としては自分が作った「芸術作品」でも、世の中に流通していく上で、ある時点で作品が商品に変わるんですよ。映画を作り続けていくには、作る段階から商品であることを考えなければなりません。映画を作り続けていくことは、観客との関係をどう作り続けていくかということです。
商業映画として考えた時に、観る人との関係が必要だと?
大友いえ、表現行為ですから、商業映画であれアート映画であれ観る人がいることを前提に映画は作られます。アート映画であればアート映画として評価する人がいる訳ですからね。ただ、映画に参加してもらうとか支えてもらおうという時には、「映画が商品として捉えられる」という視点がいると言いたいんです。
作品への眼と、観る人たちへの眼と、複眼が必要ですよね。複眼を持っている人は自分でプロデュースして、自分の応援団を自分が核になって作っていく。複眼が持てない人には観る人たちへの眼を持ったプロデューサーがいる。

なるほど。いろいろな人の想いや資金や技術がやり取りされるという意味での「商品」ですね。
大友映画会社の人でも、動画配信サービスの人でも、自分を後押ししてくれる人を認識する必要があります。作り手ひとりでは流通できませんから。ネット動画もレベルが上がって来ている。レベルの高い動画でないと観てもらえません。弱肉強食の世界で残っていくためにも、作り手と受け手の関係性を丁寧にマネージしていく必要がありますね。
(取材・構成:大竹 悠介)
(撮影:杉田拡彰)

大友 啓史 (映画監督)
1966年生、岩手県盛岡市出身。慶應義塾大学卒。NHK入局後、97年からLAに留学。2年間、 ハリウッドで脚本や演出を学ぶ。「ハゲタカ」「白洲次郎」「龍馬伝」などを演出し、イタリア賞始め国内外での受賞多数。NHK在籍時の2009年に映画『ハゲタカ』で映画監督デビュー。2011年4月NHK退局、株式会社大友啓史事務所を設立。ワーナーブラザースと3本の監督契約を結ぶ。『るろうに剣心』(12年)、『プラチナデータ』(13年)に続き、『るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編』(14年)が世界64か国2地域で上映、国内ではその年公開の邦画No.1ヒットを記録。昨年は『秘密 THE TOP SECRET』(8月公開)、『ミュージアム』(11月公開)、今年は将棋を題材にした青春映画『3月のライオン』二部作(3、4月公開)と話題作が立て続けに劇場公開された。